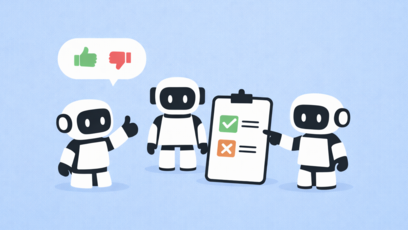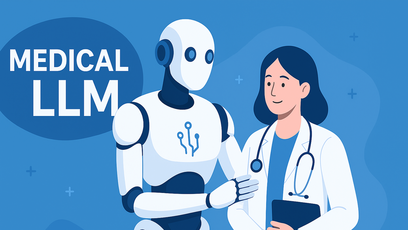Column
コラム
AI Deep Dive【33】BIツールと生成AI
2025.11.04

BI(Business Intelligence)ツールは、「データの集計・解析・見える化を容易にし、その分析結果をビジネスの意思決定に役立てるためのツール」であることをこのコラムの28回でご紹介しました。
そんなBIツールと、目覚ましい進化を続ける生成AIとの融合には、大きなメリットが期待できます。
一方で、正確性が求められるデータ分析において生成AIのブラックボックス性がどう影響するか、またデータ漏洩などのセキュリティ面の心配など、懸念事項もあります。
本コラムでは、BIツールと生成AIをかけあわせる際のメリット、デメリットをテーマとしています。
「BIツール×AI」の進化
私が初めてBIツールに触れたのは弊社で取り扱っているSpotfireで、今から10年近く前のことです。現在はVer.14ですが、当時はまだVer.6でした。バージョンアップを重ねるごとに、機能は格段に進化し、使いやすさも大きく向上しました。
たとえば加工・成型したデータがダッシュボードの内部で使いまわせるようになったり、ファイルエクスポート形式がCSVだけでなくExcelにも対応したりと、地味なものもありますが、業務効率に直結する改善が多数ありました。BIツールは、間違いなく日々の分析業務を支えてくれています。
そして最近では、Spotfireにも「Spotfire Copilot」という生成AIと連携した機能が登場しました。
ツール画面にはプロンプト画面が用意され、自然言語で対話しながらツールを操作できます。分析や使い方のサポートを受けたり、グラフの生成からお任せしたり、データ整形も可能です。かつてはツールのHELPやWeb検索を駆使して必死に情報を集め、苦労しながら作っていたあれこれが、今ではAIに聞けば一瞬で答えが返ってくる──そんな時代になりました。
現在、生成AIを搭載したBIツールは、他にも数多く登場しています。Power BI(Microsoft)、Tableau(Salesforce)、Amazon QuickSight、等々、自然言語による分析やインサイト抽出や予測分析など、ツールによって差はありますが、色々な機能を備えています。AIアシスタントの力により、可視化や分析のハードルは大きく下がり、より直感的なデータ活用が可能になっています。
「BIツール×AI」の課題
とはいえ、生成AIには避けて通れない課題があります。最大の懸念は、生成AIは「うそをつく」こと。対話形式であっという間にデータを整形・可視化してくれるのは魅力的ですが、その結果が正しいかどうか即時に判断できる材料がない場合、結局は出力結果や算出過程を人が確認する、という手間が発生します。他にも挙げられる生成AIの懸念点は、「要望が多いと取りこぼす」ところ。チャットでもAPIでもそうですが、生成AIにプロンプトで指示を出す場合、伝える要望が多すぎると、たいてい何かしら漏れが生じます。これはデータ分析という精度が求められる作業において、見過ごせないデメリットです。
弊社では、経営の収支情報や社員の時間外勤務取得状況、年休取得数などの社内データをSpotfireで加工・可視化し、「見える化サービス」として社内に展開しています。担当者が毎月最新のデータをツールに読み込ませれば、Webブラウザ経由で最新情報を表示でき、経営層を含む関係者が自由に閲覧・確認することが可能です。フィルターやドリルダウン機能を使った分析も行えます。また、部署や役職に応じた公開範囲の制限も、社員情報リストをもとに自動で制御されています。
ですが、このダッシュボードでは非常に多くの種類のデータを扱っています。特に経営データについては、弊社の会計基準に基づいて作り込まれているため、内部では複雑な計算処理を行っています。複数のデータを結合し、項目ごとに異なる計算ロジックを適用するなど、細かく複雑な処理が必要です。このようなダッシュボードを、現在の生成AIが一瞬で再現できるとは、正直まだ思えません。全く同じ仕様を満たすものを作るには、長い長いプロンプトによる対話が必要になるでしょう。
AIは“それっぽい”回答を返すことが得意ですが、“正確さ”が求められる場面では、まだ人間の目による検証が不可欠です。
「BIツール×AI」の活用
「複雑な計算処理や機能を組み込んだダッシュボードを、一瞬で仕様漏れなく構築してくれる」AIを搭載したBIツールの登場はまだまだ難しそうです。(ただしAIの進化は早いので、来年くらいには出来上がっているかもしれませんが…。)
ですが、初心者がBIツールを覚える段階では、生成AIはものすごく頼りがいのあるパートナーになります。
例えば「売上推移のグラフを作りたい」と思ったとき、どのデータを使えばいいのか、どんな可視化が適しているのか、そもそもどこをクリックすればいいのか──そんな疑問に、生成AIは対話形式で丁寧に答えてくれます。「この列を使って棒グラフを作って」「月別に集計したい」「前年比も出したい」といった要望を自然言語で伝えるだけで、ある程度の可視化まで導いてくれるのは、初心者にとってはまさに“先生”のような存在です。かつては、ツールの操作方法を理解するためにマニュアルを読み込んだり、検索しながら試行錯誤を重ねる必要がありました。しかし今では、AIとの対話によってスムーズに進められるようになり、導入のハードルが大きく下がっています。BIツールを使い始める際の「最初の一歩」を支える存在として、生成AIは非常に頼もしい味方です。そして、「製造者」ではなく「教師」としてAIを使うぶんには、「うそをつく」という問題のデメリットはかなり減ります。その答えが正しいかどうかは、人がその結果を試すことですぐに検証できます。学習支援や初期の情報収集において、生成AIはこれ以上ないパートナーだと感じています。
そんな“教師役”として生成AIを使用した経験談をひとつご紹介します。
先日、「文字列の中で特定のワードが何回出てくるかカウントしたい」ということがありました。Find関数では”何文字目に出てくるか”しかわからないし、Spotfireにそんな関数あったかしら……と考えながら、生成AIに聞いてみたところ、こんな回答が返ってきました。
・Spotfireには、文字列の中に特定のワードが出てくる回数を調べる関数は存在しますよ!
・例えば「東京」というワードを探したいなら、こんな風にできます
(Length([テキスト列]) - Length(Replace([テキスト列], "東京", ""))) / Length("東京")
・コミュニティサイトなどでもこの方法が紹介されています。リンクが知りたいですか?
……早速、少しの嘘が入っています。確かに私の要望は解決できていますが、「目的を満たす関数」が存在するのではなく、「複数の関数を組み合わせれば目的を果たせる」という回答なので、微妙に違います。 (もしかしたらこれも嘘で、実はぴったりの関数が存在している可能性も…?)
とはいえ、これを自分で実現しようと思ったら
1.Spotfireの関数一覧でテキスト関数を探す → 見つからない
2.どうすれば実現できるか考える
3.検討したアイデアを試す
という3ステップが必要になります。生成AIに質問することで、1と2にかかる時間を大幅に短縮できたのは確かです。さらに言えば、おそらく自分で2を考えるよりも、3の成功率はずっと高くなるでしょう。間違いなく便利です。
このように、作業を効率的に進めることはできますが、こうした使い方を続けていると、いずれ“考える力”や“覚える力”が衰えてしまうのでは──という不安は頭をよぎります。
生成AIとの付き合い方、うまくバランスを取りながら、使いこなしていきたいものです。
お問い合わせ
AI Deep Dive
このコラムは、NTT-ATのデータサイエンティストが、独自の視点で、AIデータ分析の技術、市場、時事解説等を記事にしたものです。
本コラムの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。