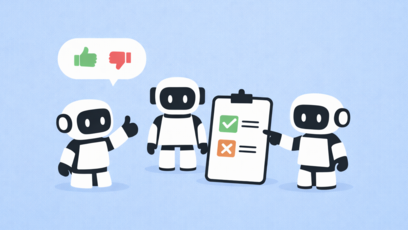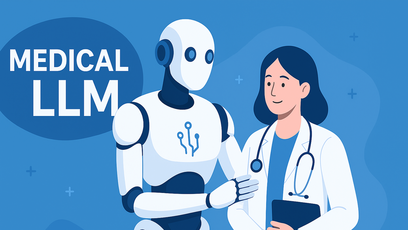Column
コラム
AI Deep Dive【32】ネットワーク運用分野におけるAI技術の導入と研究の進展
2025.10.07

スマートフォンやインターネットの普及により、私たちの生活は便利になりましたが、その裏側では膨大で複雑なネットワークが日々運用されています。こうしたネットワークを安定して運用するには、障害の予兆を見つけたり、トラブル時に迅速に対応したりすることが求められます。
そこで注目されているのが、AI(人工知能)技術です。本コラムでは、これらの技術がネットワーク運用にどのように研究・活用されているか、および今後の展望についてご紹介します。
ネットワーク現場の課題
ネットワーク運用の現場では、以下のような課題が日常的に発生しています。これらの課題は、運用者の負担や組織のリスクにも直結します。
① 障害対応の属人化とスキル継承の困難
多くの企業では、ネットワーク障害の対応がベテラン技術者の経験と勘に依存しています。その結果、以下のような問題が発生します。
- 担当者が不在の際に対応が遅れる
- 引き継ぎが難しく、引継ぎ直後の対応では品質が落ちる
属人化は、運用の安定性を脅かす要因であり、組織としての持続可能性にも影響します。
② 障害の予兆検知が困難
ネットワーク機器からは膨大なログやメトリクスが出力されますが、その中から異常の兆候を見つけるのは至難の業です。特に以下のようなケースでは、予兆を見逃すリスクが高まります。
- 一見正常に見えるが、実は徐々に性能が劣化している
- 複数の機器にまたがる微細な異常が連鎖している
- 過去に類似の障害がないため、経験則が通用しない
このような状況で障害予兆を検出し、障害発生を防止することは困難です。
③ 夜間・休日対応の負担と人的リソースの限界
ネットワークは24時間365日稼働しており、障害は時間を選ばず発生します。そのため、運用担当者は以下のような負担を強いられます。
- 夜間・休日のオンコール対応
- 少人数での監視体制の維持
- 長時間労働による疲弊と離職リスク
こうした状況は、働き方改革や人材確保の観点からも大きな課題であり、コスト増にも繋がります。
④ 構成変更のリスクと検証の難しさ
ネットワークの構成変更は、サービス品質に直結する重要な作業です。しかし、以下のような理由で慎重な対応が求められます。
- 変更による影響範囲が広く、予測が難しい
- 検証環境が本番と異なるため、事前テストが不十分
- 一度のミスが大規模障害につながる可能性がある
このような状況は、変更作業が心理的にも技術的にも大きな負担となります。
技術の紹介と実用例
ネットワーク運用におけるAI技術の導入は、すでに現場での課題解決に向けて実用化が進んでいます。ここでは、具体的な技術とその活用シーンを紹介します。
① 障害予測と予兆検知
AIは過去のログデータやトラフィックの傾向を学習することで、障害の予兆を検知することができます。たとえば、あるネットワーク機器のCPU使用率が徐々に上昇している場合、AIは過去の障害パターンと照らし合わせて「数時間以内に異常が発生する可能性が高い」と判断し、運用者に通知します。このような予測機能により、事前対応が可能となり、サービス停止のリスクを大幅に低減できます。
なお過去の障害パターンがなく正常データのみでも学習が可能な弊社ソリューションとして、@DeAnoSを販売しています。
② 自動対応と復旧支援
障害が発生した際、AIは事前に定義されたルールや過去の対応履歴をもとに、自動で一次対応を実行することができます。たとえば、特定のポートで通信が停止した場合に、代替ルートへの切り替えや再起動処理を自動で行うといった対応です。これにより、夜間や休日の対応負荷を軽減し、復旧までの時間を短縮することが可能になります。
③ トラフィック分析と異常検出
AIはリアルタイムでネットワークトラフィックを監視し、通常とは異なる通信パターンを検出することができます。たとえば、急激なトラフィックの増加や、特定のIPアドレスからの不審なアクセスがあった場合、それを即座に検知し、遮断や隔離の処理を行うことができます。この機能は、セキュリティ対策としても非常に有効であり、外部からの攻撃や内部の異常を早期に発見する手段として活用されています。
④ AIによるログの自動分類と分析
ネットワーク機器から出力されるログは膨大で、手作業での分析には限界があります。AIはこれらのログを自動で分類し、異常や重要なイベントを抽出することができます。たとえば、数百万行に及ぶログの中から、障害に関連する数十行だけを抽出し、運用者に提示することで、対応の迅速化と精度向上が図れます。
技術導入の課題と解決に向けたアプローチ
AI導入には以下のような課題があります。
- データの質と量:学習に必要なログやメトリクスが不足している、または整備されていない。
- 既存システムとの統合:レガシーなネットワーク機器との連携が難しい。
- AIの不正確性:AIの判断は誤ることがある。
これらの課題に対しては、以下のようなアプローチが有効です。
- 段階的な導入:まずは監視や可視化から始め、徐々に自動化へ移行。
- PoC(概念実証)の実施:小規模な環境で効果を検証し、現場の理解を促進。
- 精度向上:運用と並行して定期的にモデルを更新。
今後の展望
今後、AI技術はさらに進化し、ネットワーク運用の自律化が進むと予想されます。特に、以下のような展開を筆者は期待しています。
- 自己修復型ネットワーク:障害を自動検知・修復し、ユーザーへの影響を最小化。
- 自律最適化:トラフィックの増減を予測し、リソースを最適化。
- セキュリティとの融合:AIによる脅威検知と対応が、ネットワーク運用と一体化。
今後、これらの技術がさらに進化すれば、運用の効率化だけでなく、より安定したサービス提供にもつながるでしょう。ネットワーク運用に携わる方々にとって、AIは決して遠い存在ではなく、すぐそばにある「頼れるパートナー」になりつつあります。
お問い合わせ
AI Deep Dive
このコラムは、NTT-ATのデータサイエンティストが、独自の視点で、AIデータ分析の技術、市場、時事解説等を記事にしたものです。
本コラムの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。